私の親友について
- Kamome Kamoda
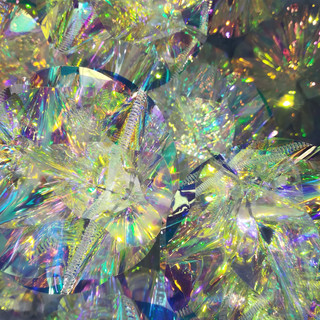
- 6月27日
- 読了時間: 10分

ニノが亡くなって、昨日で一か月が経った。いつもの窓辺に、帰ってきたときの玄関に、夏の床の間に、いつもの椅子の上に“いない”という現実は、なかなか私たち夫婦の毎日に、ぎゅっとした悲しみを感じさせる。日々、どれだけニノという小さなもふもふの猫に助けられていたかを実感する。
ところで、ニノ、という名前は彼の名前の一部である。
本当の名は「ニノ・カンカンポワ」という。動物病院で私の苗字をつけて「鴨田ニノさん」と呼ばれるたびに、いやぁ、ニノの苗字はカンカンポワなんだけどなぁ…と思って過ごしてきた。そんな風に、私に帰属しない独立した名前をつけたからなのか、彼は最初からずっと、私のペットというより私の親友として、独立した生き方をしていたように思う。それが最後の時期、かなりしんどかった時までそうであった。そんな姿に私たち夫婦は、なんて素敵な生き方だろうと思ったものである。

私たちが出会ったのは、私が二十歳になる年の8月2日だった。
当時、美大の洋画コースに所属していたが、その頃は版画コースによく出入りしていた。版画コースの雰囲気は洋画のそれと全然違っていて、私はたいそう好きだった。今でも、自分の制作の基盤たるリズムや物の使い方は、あの頃にみなさんから作ってもらったものだと感じている。
同期より、ひとつ上の先輩にとても面倒をみてもらった私は、いつも先輩たちと一緒に過ごしていた。そのなかに、Cさんという小柄で腕の長い、綺麗で不思議な女性がいた。私には恩師が様々いるが、制作中に頭に浮かぶ言葉の多くが、彼女からもらった言葉たちである。
ある日急にCさんが「猫はいいぞ、猫を飼った方がいい、きっと猫が必要だ!」と言い出し、「え???」という私の顔を見たのか見てないのか、猫がいかに素晴らしいかをとうとうと語ってくれた。たぶん2本目の煙草に火をつけるころには「で、猫飼わないか?」と言っていたと思う。あの時の彼女のニヤニヤしたうれしそうな顔を、今も鮮明に覚えている。私は自分が命を飼う責任をほぼ見つめずに、そこに待っている命と出遭うわくわく感と、Cさんがうれしそうなことがうれしい気持ちで、「飼います。」と言った気がする。Cさんは「猫と出会うってことは、事故だから!事故にあったと思って!」と喜んでいた。
女の子の猫を飼うことになると話をつけていたはずだったんだが、実際にもらいに行くと猫は男の子だった。私は、映画「アメリ」がとても好きだったので、猫の名前をアメリにするつもりだったのだが、アメリは女の子の名前だ。手のひらに収まるサイズのよく鳴くその猫をもらった帰りの車の中で、アメリの恋人のニノ・カンカンポワを名前にすることに決めたのだった。

私は実家がとても厳しい部分のある家で、猫を飼うなぞ決してできなかった。一人暮らしのアパートで飼っていることがバレたら、一巻の終わり、生きてゆけないだろうと思っていた。そういう厳しさに対しての小さな反抗を、私はいくつかしてきたけれども、その中でも煙草を吸い始めたこととニノを飼ったことは、彼らとは違う独自の世界が自らにあることを証明したい気持ちから始めたなと思う。
しかし、バレたら本当に終わる。そこで最初の2日だけニノをアパートで飼い、Cさんの当時のアパートで1年ほど預かってくれることになった。
その後も大学学部卒業まで、Cさんのシェアハウスにニノを居候させてもらった。
あの頃は特にそうだったが、Cさんが私にしてくれたことは並大抵のことではなく、愛情だけではなくお金も使って、私を助けてくれていた。特に、学部の卒業制作はCさんの家にずっといさせてもらって、最後の最後まで画面と闘わせてくれた。私が制作のストレスで神経性胃腸炎になったときも、私を丁寧に介抱してくれた。ありがとうという言葉では到底まかないきれない量の感謝を感じている。
そういえば、今でもよく覚えているんだが、Cさんに1年ほど預かってもらった後、久しぶりにニノに会ったときのことである。
Cさんのシェアハウスで、みんなが集まる居間から出ると、階段のところにニノがいた。ニノに「覚えてる?」と言いながら一緒に遊んでいると、急に眠くなって、ニノを胸の上に置きながら、階段を椅子のようにして眠りこけてしまった。居間から先輩が出てきて「こんなところで!?」と言うまで、私たちはそのままお互いの心臓をくっつけながら寝ていた。
あの時に初めて、私とニノはひとつのチームになったような気がしている。

大学学部卒業からの人生には、常にニノがそばにいてくれた。
京都、東京、山形、滋賀と引っ越し、多くの人に協力をいただきながら、どうにか一緒にやってきた。私たちはキキとジジのように、新しい土地で新しい人と生活するなか、家の中では私たちがふたり、静かに物語を紡いでいた。
私はニノ以外の猫をほぼ知らないけれど、彼はほとんど私の言葉がわかったし、気持ちも丁寧に察する子だった。話しかけると鳴き声やしっぽ、動作で答えて、だいたい会話ができた。もちろん私は猫語がわからないし、ニノも言葉の何を解っていたのかはわからない。けれど本当に、ほぼ、彼はわかっていたと思う。
それに制作途中の絵の上には絶対に乗らなかった。制作中も私が見える場所で寝ていた。縫物や編み物、読書、書類仕事は基本的に私と制作物の間に入るけれど、絵を描いている時は絶対に邪魔をしなかった。ニノは、全部わかっていたのだと思う。
そしてなぜか、夫のことが大好きだった。私と夫は、私がニノと出会った1年後に出会って、お付き合いをした。それから何度か別れているが、なぜかまた何度か付き合い、そして結婚した。
私には別れている間に恋人ができることもあったが、初めて夫以外の恋人をニノに紹介した時は、ベッドの上に四つ足を踏ん張って「ニャー!!!!」と威嚇していた。ニノとその人も、最終的にとても仲良くなったけれども(そしてそれはとても素敵な時間だった)、ニノは夫以外には最初にそういう振る舞いをする。やっぱりニノは、全部わかっていたのだと思う。

私は、そんなニノを、私が病気の時にすごくぞんざいに扱った。あの頃の私は、眠れず、食事もコントロールができず、髪の毛も抜けて、死と至近距離でチキンレースをしているような地獄のような日々だった。自分が生き残ることで精いっぱいだった間、私はニノにひどく寂しい想いをさせた。それが今でも、申し訳なく心に残る。
病気が少しおさまってきた頃に、滋賀に引っ越した。病気の間、本当に寂しかったろうに、私が頭痛や腹痛がすると、ニノは、その痛みの近くに身体を寄せてくれることがあった。しんどくて泣いていると、知らぬ間に膝をあたためてくれることがあった。寂しくてニノの前足に手を伸ばすと、きゅっと握り返してくれることもあった。
後々、その姿にどれだけ助けられたかをニノに語って聞かせたことは何度もあるのだけれど、その度にニノは、私の自責的な思考を感じたのか「うるさい、もういい」みたいな感じで窓辺へ行ってしまうのだった。それより「ニノ~!大好き!」と表現している時こそ、彼は嬉しそうにゴロゴロ言って喜んでくれた。
ニノは自分のしんどさを傍に置いてでも、愛を伝えることを決して辞めない。私の喜びを喜びとして感じてくれる、潔くて格好の良い在り方をしていた。

その姿は、最後の最後までそうだった。
最後の2週で毛繕いができなくなり、最後の1週間はずっと吐血していた。相当にしんどかったはずなのに、彼に「愛してるよ、ニノ」と声をかけると、尻尾がぽふん、と動いた。
アイヌのコタン(村)では、村の人が亡くなりそうになると、村中の人が代わりばんこに亡くなる方を撫でにくるらしい。撫で、ゆすり、歌うのを、三日三晩するそうだ。自分が人生で愛した人たちの手のひらで温めながら逝くなんて、なんて美しいんだろうと、ずっと憧れていた。
幸いにして、ニノにも最期の時間に、私と夫でたくさん撫で、たくさん声をかけることができた。ニノは痙攣する体で、声がうまくでないにも関わらず声を出して、2人の手で温められながら逝った。
亡くなったはずなのに、ニノの身体は全くしんどそうではなく、モノになったという感じもなく、異常に愛おしかった。夫は「愛の残滓がすごすぎる」と言っていたが、これを愛の残滓と言わずになんと表現しようと思うほど、ただただ美しくて、愛のキラキラの粒子でニノが繭に包まれているように感じられていた。
そう、亡くなったにも関わらずまだ私たちはニノに“愛されている”と感じさせられていた。
愛おしいとかの、こちらから向けるポジティブな感情を遥かに超える量で、ニノから“愛されている”感じがする。それが、今も続いている。
命が亡くなる時、いつも、その命が全てをかけて愛する人にギフトを贈るように思う。それは気づかせてくれることだったり、強い決意や誓いを促すことだったりもするけれど、最も大きなものが相手から“愛されている”という体感なのかもしれない。

ニノに、今も“愛されている”という体感はもちろんまだある。
これはきっと、私の中にあるニノが刻んでくれた記憶が、今も私に愛を感じさせてくれるんだと思う。けれど冒頭にも書いたように、彼が現実にはいないことを、毎日ふとした瞬間に思い知らされる。目で見る「いない」という現実の説得力は、私の体感を軽々しく否定してくる。私が今も“愛されている”のは幻想なのかもしれない、と、記憶が薄れていくような、心許ない感じがあるのだ。
だから昔から人は、絵を描いたりアクセサリーを作ったりすることで、見えない、心許ないパワーを、見えて、確かなものにするんだろうと思う。それが依り代のようになって、記憶や想いを留めるツールになってくれる。
そう思ったとき、これまで調べてきたたくさんのお守りへの想いは、自分が考えていたよりもっと多重に、深く存在しているように感じた。古代の人が牙をアクセサリーにするという振る舞いは、ただ力のあるものを身に着けようと考えたという単純な問題ではなかったのかもしれない。それらが切り裂いたたくさんの血肉や、先ほどまで生きていたその生き物の吐息、温かさ、湿り気、それを捕ることを誇りに思った人の想い、それを見つめる人の想い、いろんなものが折り重なって力の“象徴”になっていくのかもしれない。
今までその振る舞いをリスペクトして制作していたつもりだったが、よりそれを知ることができたように思う。
ニノ、今どうしてるだろう。49日まではまだ我が家の窓辺にいてくれているだろうか、それとも、私のそばで丸まっていてくれているだろうか。
ニノは、今まで私の汚い部分、卑しい部分をたくさん知ってきたけれど、それでもずっと、本当の意味で私を愛してくれていた。私の役割や、特性など何も気にせずに、ただ、私という一つの命を、全身全霊で愛してくれていた。これは、自分なんて消えてしまった方がいいと、自責的な思考で自らを傷つけてきた私にとって、まごうことなき宝物なんだ。まだ、自分を傷つけてしまうことはあるかもしれないけれど、そのたびに私はあなたを思い出す。あなたが愛してくれた私を、私は蔑ろにしないように、毎日、毎度、あなたのかわいい瞳を思い出す。やわらかい毛並みを、温かくていい匂いのするあなたのお腹を思い出す。
私は、自分の命を使うならば、絵を描くこと、作ることだと思ってきたのに、ずっと怖くて、誰かに馬鹿にされる、拒否される、愛されないと、作品を表に出すことができなかったけれども、もうそれも辞める。私の心にはあなたがいる。あなたにもらった愛は、自分の中に巣くう呪いをほどく鍵にする。
ニノ、もしもう一度ニノが生まれ変わったら、もう一度一緒にいさせてほしい。今度は決してぞんざいに扱う時間など作らない。一緒においしいものを食べて、風を感じて、温かくして寝よう。私は私を守って、しっかりと生きてゆくから、もう一度一緒にいてもいいなと思えたら、一緒に生きよう。
ありがとうニノ、あなたほどの親友がいてくれて、本当に幸せだった。



